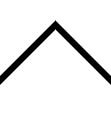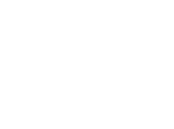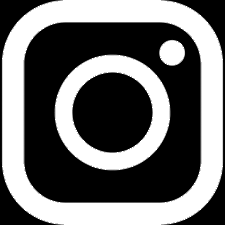岡山で暮らす知恵
岡山の里山暮らし
高梁市・吹屋重要伝統的建造物群保存地区

ベンガラ色の街並み
岡山県西部吉備高原上の山間地に位置する吹屋は、銅山とベンガラで繁栄した鉱山町です。大正ロマンを思わせる景観に特長があるハイカラな街並みは、1977年(昭和52年)に国の伝統的建造物群保存地区に指定されました。起伏の多い丘陵上の往来に沿って、町家主屋や土蔵等が建ち並んでいます。屋根は赤褐色の石州瓦で葺かれ、赤い土壁や白漆喰壁の平入・妻入の町家が混在しています。

吹屋郵便局

旧片山家住宅
岡山県高梁市成羽町吹屋
1759年の創業以来200年余に渡って弁柄(ベンガラ)の製造・販売を手がけてきた。現在でも弁柄が栄えた江戸時代末から明治時代の屋敷構えを残しています。






郷土館
岡山県高梁市成羽町吹屋367
ベンガラ窯元片山浅次郎家の総支配人片山嘉吉(当時吹屋戸長)が分家され、本家の材木倉より良材を運び、石州の宮大工・島田網吉の手により1879年(明治12年)完成しました。





旧吹屋小学校

旧吹屋小学校
岡山県高梁市成羽町吹屋1290-1
旧吹屋小学校は、1873年(明治6年)に開校し、1899年(明治32年)に吹屋尋常高等小学校と改称し現在の場所に移転。1900年(明治33年)に木造平屋建の東校舎・西校舎が落成しています。2012年(平成24年3月)まで国内最古の木造校舎として使われており、保存修理工事を実施し、2022年(令和4年)4月から岡山県指定重要文化財として一般公開されています。


旧吹屋小学校 2階教室
西江家住宅

西江家住宅
岡山県高梁市成羽町坂本1604
西江邸は、高品質なベンガラの礎となる本山鉱山を開抗ベンガラの原料となるローハとベンガラの大量生産を行った豪農商・西江家の邸宅です。
西江家は江戸期には惣代庄屋として天領地の支配を許され、代官御用所を兼ねていました。江戸繁栄期の趣を今に色濃く残す西江邸は、郷蔵・お白洲跡・駅馬舎・手習い場などを残す大変貴重な歴史的文化建造物です。この邸宅は西江家が代々受け継ぎ、現在も18代当主が住まう活きた文化財です。
現存する建物は、宝永・正徳年間(1704~1715年)の創建です。
休館日 不定休 ※事前予約制
特別見学 1,650円(税込)18代当主の説明(お茶・お菓子付き)※事前予約制

旧広兼家住宅

旧広兼家住宅
岡山県高梁市成羽町中野2710
広兼家は、江戸時代後期に小泉銅山(現在の高梁市成羽町小泉)の経営と弁柄関連の製造で繁栄しました。2階建ての大型主屋や土蔵長屋等は文化7年(1810)に建てられたもので、楼門を持つ豪壮な石垣は城郭のような屋敷構えとなっており、市の重要文化財に指定されています。





備中松山
備中松山 武家屋敷

岡山県高梁市石火矢町 城下町の山側は武家屋敷が立ち並んでいる。
旧折井家
高梁市石火矢町23-2
折井家は、当時160石の馬回り役を勤めた武家の家柄です。旧折井家住宅は、江戸時代後期に建てられたもので、庭に面して資料館があります。江戸時代中期の建てられた建物は、寺院や数寄屋風の要素を取り入れた珍しい造りとなっており、市の重要文化財に指定されています。


旧埴原家住宅
岡山県高梁市高梁市石火矢町27
埴原家(きゅうはいばらけ)は、江戸時代中期から後期にかけて、近習役や番頭役などを勤めた120石~150石取りの武家の家柄です。漆喰壁の格式漂う住宅は、江戸時代後期に建てられました。


備中松山城下町 高梁本町
(松山往来起点)
慶長10年代(1605~1614)に小堀正次、政一(遠州) 親子が備中国奉行(備中代官)として着任してから備中松山城の修薬と備中国特産物の生産、集荷及び家臣団の需要に対して、家中屋敷(武家屋敷)の西、松山川(高梁川)に沿って、城下町づくり(町家)に着手したのが「本町」の誕生です。
その後、水谷時代(1642~1693)(寛永~元禄)に資源開発、物流の大動脈として松山川(高梁川)の航路整備と高瀬舟の発着場を本町と下町につくったことで、物流の中心として本町に、あらゆる業種の有力商人が集まり、経済活動の中核地域とし賑わいました。

本町通りは城下町の町割りの中で最初にできた通りと言われており、今でもその名残を残しています。

岡山県高梁市本町 高梁川沿いに、商家の街並みが続いている。
商家資料館・池上邸
岡山県高梁市本町94
古い商家の並ぶ本町通りでひときわ目を引く池上邸は、享保年間八代将軍吉宗の頃、この地で小間物屋をはじめ、その後、両替商、高瀬舟の船主等を経て、醤油製造で財をなした豪商の家です。


商家資料館・池上邸 庭園
旧閑谷学校
旧閑谷学校
岡山県備前市閑谷784
旧閑谷学校は、岡山藩主池田光政が、庶民の教育を目的として寛文10年(1670)に設立した郷学である。徳川光圀・保科正之とならんで天下の三名君と称された池田光政は、藩政の目標を儒学の教える仁政におき、正保2年(1645)には、中江藤樹の高弟熊沢蕃山に命じ、岡山城下花畠で藩士に陽明学と武芸を修業させた。その後、本格的な家臣教育の機関として、寛文6年(1666)に城内の石山に「仮学館」を建設し、同9年には西中山下に岡山藩学校を開設した。また、庶民の子弟に対しては、寛文8年(1668)に領内123ヵ所に手習所を設置したが、財政難により延宝3年(1675)にはその全てを廃止して、この閑谷の地に統合した。

閑谷学校の名声は、古くから天下に聞こえていたようで、高山彦九郎・菅茶山・頼山陽・大塩平八郎・横井小楠などの学者文人なども来遊しており、大鳥圭介などの藩外からの来学も多かった。

寛文6年(1666)、光政は領内を巡視してこの地に至り山水閣静にして読書講学にふさわしい場所であるとし、寛文10年仮学校を開設し、この地の旧名木谷村「延原」を「閑谷」と改め、家臣津田永忠に後世にまで残る学校の建築を命じた。現在目にすることのできる閑谷学校の姿が完成したのは、光政没後の元禄14年(1701)、二代目藩主綱政の治政のもとで、創建当時の姿をほぼ完全に残しているものとして特別史跡に指定されています。さらに、建造物等二五件が重要文化財に指定されており、中でも、講堂は学校建築として国宝に指定されています。
学校は周囲を765メートルに及ぶ石塀で囲み、南側に校門(鶴鳴門) 公門(御成門)・飲室門・校厨門の四門を備え、中に聖廟・閑谷神社(芳烈祠)・講堂・小斎・習芸斎・飲室・文庫などが配置されています。備前焼きの赤瓦がまわりの緑にはえて美しく、石塀とともに閑谷学校特有の景観を醸し出しています。


かつては火除山をへだてて西側に学房(寄宿舎)が配置されていたが、現在は明治38年(1905)に建築された旧制の私立(後に県立) 中学校の校舎であった資料館があり、館内には創学以来300年以上にわたって継続している閑谷学校の歴史を振り返ることのできる数々の資料を展示しています。石塀の南には東西にのびる津池があり、重要文化財に指定されている石橋(津橋)がかかっています。さらに、1.2キロメール南方には当時の学校の一の門であった石門が四分の三ほど土に埋もれて現存しています。